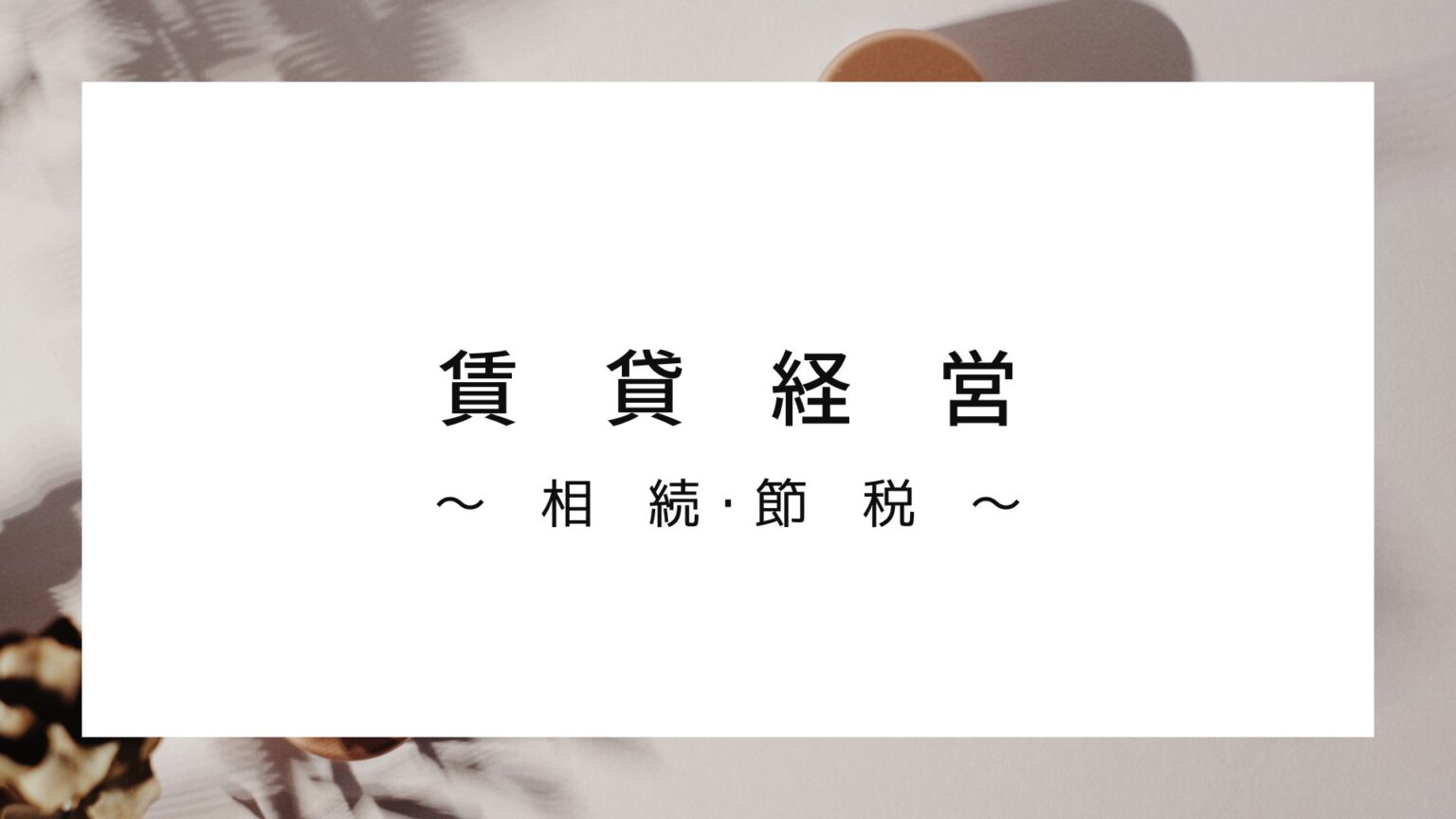最近、不動産小口化商品という言葉をよく耳にしませんか?
ひと言に「不動産小口化商品」といっても、不動産特定共同事業法に基づく小口化商品や、不動産信託受益権を活用した小口化商品など、様々な小口化商品があります。
ここでは、不動産小口化商品とはどのようなものか、その種類やメリット・デメリットについてわかりやすく解説します。
1.不動産小口化商品とは
少額から投資できる不動産証券化商品のひとつ
不動産小口化商品とは、少額から投資できる不動産証券化商品の一種です。不動産を裏付け資産として組成された商品で、個人投資家でも手が届きやすい金額から参加できるのが特徴です。
主な商品形態は以下の3つがあります。
|
商品形態 |
説明 |
|---|---|
|
匿名組合型 |
不動産会社が事業者となり、出資者が匿名組合員となる形態 |
|
任意組合型 |
不動産会社と出資者が任意組合を組成する形態 |
|
信託受益権型 |
不動産を信託し、その受益権を販売する形態 |
いずれの形態も、少額から参加でき、不動産への直接投資に比べてハードルが低いのが魅力です。投資家は出資した金額に応じて収益を得ることができます。
匿名組合型
匿名組合型の不動産小口化商品とは、事業者(営業者)が不動産事業を行い、その運用収益を出資者(匿名組合員)に分配する仕組みです。「不動産クラウドファンディング」はこの匿名組合型に分類されます。
出資者は匿名組合契約に基づき出資するのみで、不動産の管理・運営には関与できません。しかし、出資金額に応じたリスクを負うこととなります。
少額から出資が可能で、短期の運用期間も選択できるのが特徴です。
|
項目 |
内容 |
|---|---|
|
出資者の地位 |
匿名組合員 |
|
運用の決定権 |
事業者(営業者)のみ |
|
出資者の権利 |
運用収益の配当請求権のみ |
出資者は運用益を得られる一方で、事業者は柔軟な資金調達が可能になるというメリットがあります。
任意組合型
任意組合型の不動産小口化商品は、事業者と投資家が任意で組合を設立する形式です。組合契約に基づき、事業者が不動産の取得・運用を行い、その収益が投資家に分配されます。
現物出資の場合は実際に不動産の共同所有者となることから、相続税は実物不動産と同じく相続税評価額で計算されます。また、金銭出資の場合も、不動産の共同所有者にはなりませんが、不動産と同じ相続税評価額で計算できるというメリットがあり、相続税評価額を低く抑えることができる可能性があります。そのため、相続対策として活用できます。
|
特徴 |
説明 |
|---|---|
|
設立が容易 |
契約書を作成するだけで組合を設立できる |
|
柔軟性が高い |
組合員の出資比率や収益分配ルールを自由に設定できる |
|
非公募が可能 |
一般公募の手続きが不要で、少人数での運営が可能 |
匿名組合型と任意組合型の比較
|
|
匿名組合型 |
任意組合型 |
|---|---|---|
|
事業主体 |
事業者 |
出資者(共同事業) |
|
出資金額(※) |
1口数万円程度~ |
1口100万円程度~ |
|
運用期間 |
数カ月程度~10年以内 |
約10年~数10年 |
|
特徴 |
|
|
信託受益権型
信託受益権型は、信託銀行などの受託機関に不動産を信託し、その信託受益権を証券化して販売するタイプです。
|
特徴 |
内容 |
|---|---|
|
販売方法 |
一般公募や私募など |
|
期間 |
通常5~10年程度 |
|
換金性 |
成熟した投資市場がなく換金性は低い |
投資家は信託受益権を購入することで、間接的に不動産の収益に投資できます。受託機関が不動産の管理・運営を行うため、投資家は手間をかけずに不動産収益を得られるメリットがあります。一方で、受託手数料が発生するデメリットもあります。
信託期間終了時に不動産が売却されれば、投資元本とその期間の収益が分配されます。長期運用を前提としている商品が多く、中途解約ができないので注意が必要です。
2.不動産小口化商品のメリット
相続税評価額の圧縮効果が期待できる
現金や有価証券を相続すると、その金額がまるまる相続税の対象となります。一方、同じ金額で購入した不動産を相続した場合、その土地は路線価を、建物は固定資産税評価額を用いた評価方法による「相続税評価額」が相続税の対象となります。これにより、現金の時のおよそ70~80%の圧縮効果が期待できます。
相続人への均等・均質な財産分配が可能になる
不動産小口化商品では、不動産を小分けにして証券化しています。そのため、例えば1億円の物件を100口に分けた場合、1口あたり100万円となります。相続時に不動産を分割する必要がなく、相続人全員に等しく証券を分配できるのが大きな魅力です。
|
物件価格 |
口数 |
1口あたりの価格 |
|---|---|---|
|
1億円 |
100口 |
100万円 |
従来の不動産相続では、建物の一部を切り取ることができず、相続人間での資産の均等分配が難しい場合がありました。しかし証券化された不動産小口化商品なら、全相続人に対して均等・均質な財産分配が可能になります。
管理・運用の手間が省ける
不動産小口化商品の大きなメリットは、不動産の管理・運用の手間が省けることです。
一般的な不動産投資では、以下のような手間がかかります。
|
管理・運用の手間 |
内容 |
|---|---|
|
入居者募集・入退去対応 |
募集広告の出稿、内見対応、契約手続き |
|
賃料徴収・延滞管理 |
毎月の賃料請求、延滞時の督促・解約手続き |
|
建物・設備の維持管理 |
定期的な点検、修繕工事の手配 |
一方、不動産小口化商品では、運用会社が不動産の管理・運用を一括して行うため、オーナーは上記の煩雑な作業から解放されます。オーナーは出資した元本の範囲内で、不動産からの賃料収入を得ることができるのです。
ただし、運用会社への委託手数料が発生する点は留意が必要です。手数料率は商品によって異なりますが、概ね年率1~2%程度が相場です。
3.不動産小口化商品のデメリット
利回りが一般の不動産投資より低い傾向
不動産小口化商品の利回り(年収益率)は、一般的な不動産投資に比べるとやや低めに設定されていることが多いです。その理由として、主に以下の点が挙げられます。
運用会社への報酬の支払い 不動産小口化商品では、運用会社が収益の一部を報酬として受け取ります。一般の不動産投資の場合、自ら運用するので報酬は発生しません。このため、投資家への分配額が減り、投資利回りが低下する傾向にあります。
利回りが低めでも、相続対策や管理・運用コストの軽減などのメリットを享受できることから、不動産小口化商品への注目が高まっています。
利回りについて詳しくはこちら↓

換金性が低く中途解約できない
不動産小口化商品の大きなデメリットとして、一般市場がないため換金性が低いことが挙げられます。
|
商品種類 |
換金可能性 |
|---|---|
|
匿名組合型 |
原則不可 |
|
任意組合型 |
組合員の合意が必要 |
|
信託受益権型 |
原則不可 |
上記の表にあるように、匿名組合型と信託受益権型では中途解約や換金は原則不可能です。任意組合型でも組合員全員の合意が必要となるため、極めて換金が困難です。
つまり、不動産小口化商品に投資した資金は、運用期間終了までロックアウトされることになります。運用期間は概ね5年から10年程度が一般的です。
したがって、万が一の場合の資金化は難しく、換金性の低さがデメリットとなります。投資に際しては、ロックアウト期間中の資金の出し入れができないことをあらかじめ理解しておく必要があります。
自己資金が必要(融資が使えない)
不動産小口化商品への投資には自己資金が必要となります。一般の不動産投資と異なり、融資を利用することはできません。
つまり、以下の点にご留意が必要です。
-
投資に必要な全額を自己資金で用意する必要がある
-
自己資金が不足する場合は投資できない
不動産小口化商品への投資では自己資金が前提となるため、投資家の資金計画が重要になります。
4.おすすめの人
相続対策を検討している人
不動産小口化商品は、相続対策を検討されている方にとって有効な選択肢となります。
不動産小口化商品は、相続税の評価額が圧縮されるメリットがあります。相続税の評価額が小さくなれば、相続税の負担も軽減されます。
|
現金 |
不動産小口化商品 |
|---|---|
|
課税対象:金額100% |
課税対象:相続税評価額 70~80% |
また、不動産を売却する必要がなく、相続人に均等かつ均質な財産分配が可能になります。従来の不動産相続では、現物資産を分割することが難しく、金銭の分配に不平等が生じがちでしたが、不動産小口化商品であれば受益権の分配で解決できます。
管理・運用を任せたい人
さらに、不動産の管理・運用の手間から開放されるため、安定的にキャッシュフローを手にできるというメリットもあります。
このように、不動産小口化商品は相続対策の有力な選択肢と言えるでしょう。ただし、デメリットもあることを忘れずに、総合的に判断する必要があります。